食品の表示・広告の適正化を図るため、12月1日より、消費者庁は農林水産省、財務省並びに都道府県・保健所等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康増進法の規定に基づき、全国一斉に食品表示の取締りを行っています。
この一斉取り締まりは、夏期(7月)と年末に継続実施されています。
今年度年末の表示の適正化等に向けた重点的な取組については、いわゆる「健康食品」の監視指導、くるみの特定原材料への追加、経口補水液と誤認される恐れのある表示への対応等について指導、啓発に重点が置かれています。
食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、食品衛生の監視指導を強化していましたが、この時期に合わせ、食品表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に関する取り締まりの強化を行うものです。
また、景品表示法等の他法令に違反しているおそれのある表示を確認した際には、担当部署に情報提供するなど、適切な連携対応するよう要請しています。
今回の監視指導における重点事項と、令和6年度夏期一斉取締りの結果概要について確認します。
—————————————
食品表示の適正化に向けた取組について
(消費者庁 2024年11月28日)https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms203_241128_04.pdf
—————————————-
【年末一斉取締りの実施について】
実施時期:2024年12月1日から同月31日まで
主な監視指導事項:
●アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
●保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
●生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
●道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
●食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発
例年の年末一斉取り締まりの監視指導事項を、概ね引き継いだ内容となっています。
今回の監視指導および啓発活動における重点事項は次の通りです。
(1)いわゆる「健康食品」の監視指導について
いわゆる「健康食品」について、食品表示基準第9条および第23条の表示禁止事項に特に留意の上、食品関連事業者等に対する監視指導を徹底すること。
小林製薬「紅麹サプリ」をめぐる健康被害問題を受け、2024年8月に食品表示基準が改正され、機能性表示食品制度等の見直しが行われた。
(2)くるみの特定原材料への追加及び特定原材料に準ずるものの取扱いについて
2023年3月に特定原材料として追加された「くるみ」を表示することの徹底(経過措置期間2025年3月31日まで)、特定原材料に準ずるカシューナッツは木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加などが認められていること、マカダミアナッツは2024年3月28日付けで新たに特定原材料に準ずるものに追加されたことから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等に対して、可能な限り表示することを促す。
(3)「乳児用規格適用食品である旨」の表示の周知啓発について
「乳児用規格適用食品である旨」の表示は、単に「乳児用規格適用食品」と表示すると、その趣旨が正確に消費者に伝わらないおそれがあり、2023年6月に「食品表示基準について」の一部改正により、「乳児用規格適用食品」から「乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品)」と表示方法が改正された。
他方、乳児用食品としての放射性物質の規格が適用される食品であることが容易に判別できる食品については、表示を省略できることとされ、乳児用食品は全て表示を省略できることを併せて明確にし、単に「乳児用規格適用食品」の表示がなされることのないよう、食品関連事業者等への周知啓発を図る。(経過措置期間2025年3月31日まで)
1)「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)の一部改正について(令和5年6月29日消食表第343号)(PDF)
https://www.baby-food.jp/news/1.pdf
2)「食品表示基準Q&A」の一部改正について(令和5年6月29日消食表第344号)(PDF)
https://www.baby-food.jp/news/2.pdf
3)乳児用規格適用食品の表示に係るアンケート調査((独)国民生活センター、令和3年10月19日)(PDF)
https://www.baby-food.jp/news/3.pdf
(4)経口補水液と誤認されるおそれのある表示への対応に関する周知啓発について
「経口補水液」について、2023年5月に特別用途食品の表示許可制度が改正され、特別用途食品の病者用食品の中の「許可基準型」病者用食品として、新たに「経口補水液」の許可区分が新設された。
許容される特別用途表示の範囲は、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適する旨」となり、特別用途食品の許可を得ずに「経口補水液」と表示した場合は、健康増進法第43条第1項及び第65条第1項違反(誇大表示の禁止)となる。
経過措置期限の2025年5月までの間に、必要な許可を取得するなどの対応を終えるよう、食品関連事業者等に対する周知を図る。
・「経口補水液」表示には特別用途食品の許可を。無許可製品の対応は2025年5月末までに(2023年5月19日「特別用途食品の表示許可等について」一部改正)
(5)外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供に係る啓発資材の活用について
(6)その他
① 食品リコール(自主回収)に係る主な発生原因を踏まえた注意喚起について
② 食品添加物の不使用表示について
③ 遺伝子組換え食品に関する表示制度の周知啓発について
④ 原産地及び原料原産地名表示の適正化について
⑤ 健康食品の表示の適正化について
————
【令和6年度夏期一斉取締りの結果概要】
食品表示法の措置件数:
(食品衛生法、健康増進法、JAS法に規定されていた食品表示に関する規定を統合)
「命令」、「指示」ともに0件。「命令及び指示以外の措置」は2,251件。
監視指導施設数、違反件数等:
監視指導延べ施設数180,952。うち、表示違反が確認された延べ施設数2,436。
食品表示法「命令及び指示以外の措置」2,055件。食品衛生法「命令以外の措置」6件。
収去した食品等の検体数、違反件数等:
収去検体数10,266。 うち、表示違反検体数217。
食品表示法「命令及び指示以外の措置」196件。食品衛生法「命令以外の措置」0件。
違反事項別件数

————-
令和6年度食品衛生法等の表示に係る夏期一斉取締り結果について (消費者庁 2024年11月)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms203_241128_04.pdf
———–
表示管理体制をしっかりと見直しましょう。
《関連記事》
・年末一斉、食品表示の取締り。猶予期限が来年3月末に迫った食品表示新基準への移行指導等を重点に。(2019年12月 消費者庁)
・夏期一斉食品表示の取締り。消費者へのダイエット健康食品に関する注意喚起(2019年7月 消費者庁)
・年末一斉、食品表示の取締り。蜂蜜の乳児ボツリヌス症の予防対策、食品表示新基準への移行指導が重点に。(平成30年12月 消費者庁)
・夏期一斉食品表示の取締り。原料原産地表示、カンピロバクター食中毒対策に注意!
(平成30年7月 消費者庁)
・特別用途食品、プエラリア健康食品の監視指導が重点に。年末一斉、食品表示の取締り(平成29年12月 消費者庁)
===================================
◆フィデスの美・健広告法務オンライン講座◆
法律を「知っている」から、実務で「判断」「活用」
できるコンプライアンス対応力向上を図ります。
詳細はこちら
===================================
===================================
◆フィデスの広告法務コンサルティング◆
消費生活アドバイザーが、貴社の広告コンプライアンス
体制構築をサポートします。
詳細はこちら
===================================
————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの更新情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————


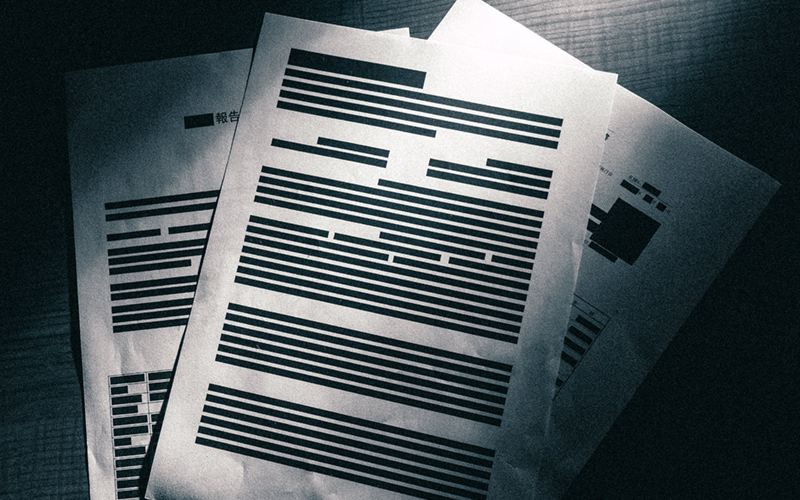
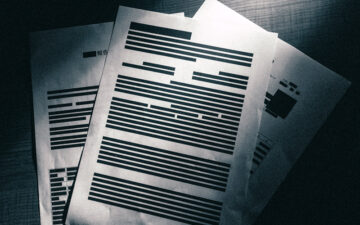
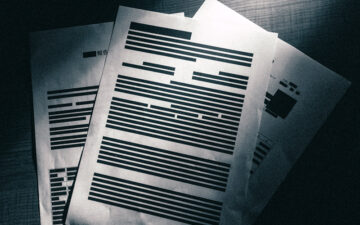

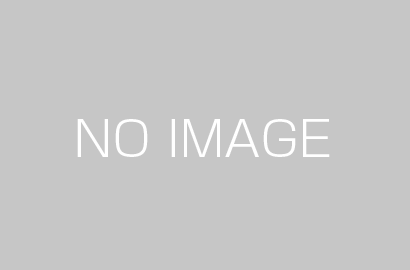
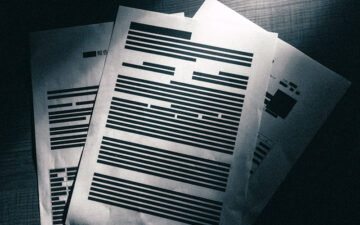

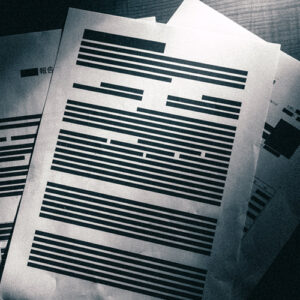
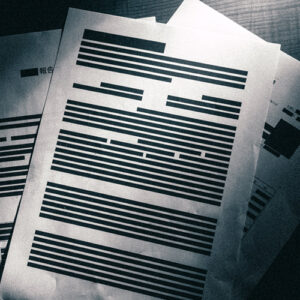




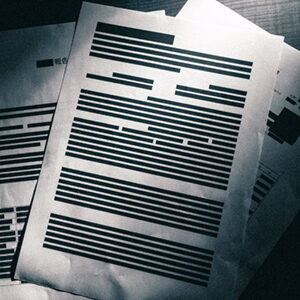






この記事へのコメントはありません。