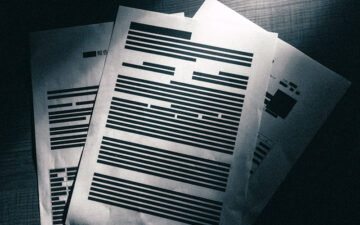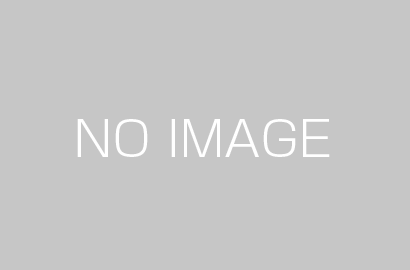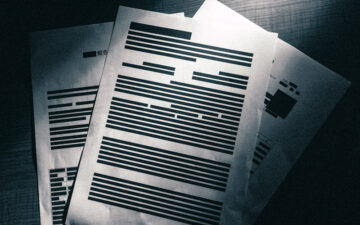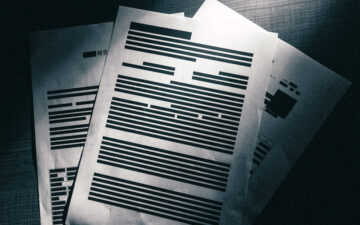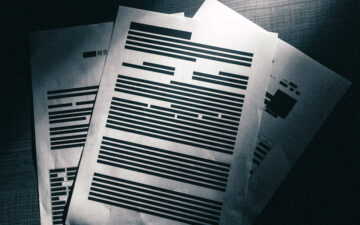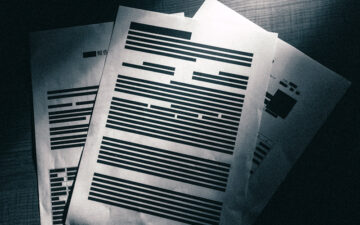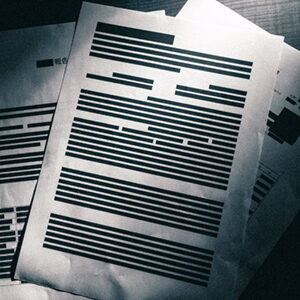今回のトピックはGI制度と日本の農産品に対する海外でのブランド棄損」について。
「八丁味噌」のGI登録を巡り、八丁味噌発祥の愛知県岡崎市が拠点の老舗2社の登録が認められず、近代的な製法も用いる県の生産者団体(県組合)が登録されたことが紛争となっています。
この「GI制度」とは、地理的表示(GI)保護制度のことで、品質、社会的評価その他の確立した特性が、産地と結び付いている農産物や食品を国がブランドとして保護する制度で、2015年6月に施行されました。
すでに「夕張メロン」や「神戸ビーフ」など、59の名称が登録されています。
名古屋メシといえば「八丁味噌」無しに語ることはできない!と思われるほどのローカルフードですね。
私も味噌煮込みのきしめんや、みそカツなど大好きです!
で、ちょっとニュースを聞いただけでは、伝統的な厳しい条件での製法にこだわる老舗の商品が正統ブランドとして国のお墨付きがもらえないことに、一消費者としても違和感を覚えて気になりました。
しかし、もう少し調べてみると、日本の農産品に対する海外でのブランド棄損が背景にあるようです。
日本の農産品の名称は、中国内で第三者が商標登録し、日本の生産者団体が使用できない例が相次いでいます。今回の「八丁味噌」に関しても、中国の業者が出願した「八丁」の商標が登録されています。
登録された商標を差し止めるには、多大な費用や手間のかかる訴訟が必要です。
GI制度の狙いとして、「地域共有の財産として、地域の生産者全体が使用可能で地域活性化につなげる」「ブランド侵害に対し訴訟等の負担なく、自分たちのブランドを守る」という観点があります。
今回の農水省の判断は、GI制度として大括りに日本の食品ブランドを守るという視点での判断だったのではと推察します。
農水省は、老舗2社に対し、県組合の基準を受け入れ、GIの使用団体として追加登録するよう求めており、老舗2社の製法は県組合の基準をより厳しく実施するもので、製造工程などを変更する必要はないとしています。
「同じGIでも、老舗2社は発祥の地を明示するなど、県組合の製品と差別化した表示も制度上、可能だ。」ということなので、ここは何とか折り合ってほしい気がします。
◆「八丁味噌」GI登録で対立 愛知県内の2組合 中国も商標出願
(SankeiBiz 2018年2月20日)
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180220/mca1802200500002-n1.htm
《関連記事》
・農産物の地域ブランドを国が後押し。「地理的表示(GI)保護制度」開始
===================================
◆フィデスの広告法務コンサルティング◆
消費生活アドバイザーが、貴社の広告コンプライアンス
体制構築をサポートします。
http://compliance-ad.jp/service03/
===================================
————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの更新情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————