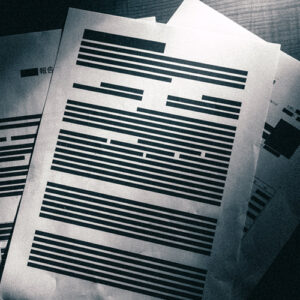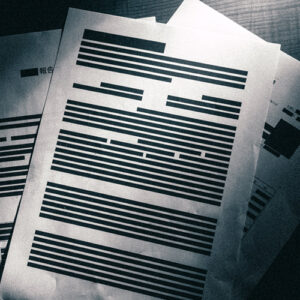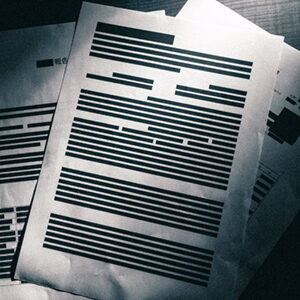この記事は会員限定記事です。ご覧になりたい方は会員登録をお願いいたします。 管理者の承認後に会員記事が閲覧できるようになります。
ご登録受付メールが、ご記入いただいたメールアドレス宛に届きます。 万が一届かない場合は、入力違いなど、ご入力いただいたメールアドレスに送信できないトラブルの可能性がございます。ご確認の上、お手数ですが再度ご登録お願いいたします。
※法人様向けのサービスとなります。gmailやyahooメール等のフリーメールでの登録はお断りしております。 正式な会社名、お名前でのご登録をお願いします。 同業者様のご登録はお断りさせていただくことがございます。